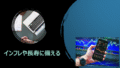9月になっても残暑は体に負担をかけます。特にシニア世代は水分調整機能や体温調節能力の低下により熱中症リスクが高く、この時期の健康管理が重要です。夏バテで体力が低下している状態での残暑は体調不良を招きやすいため、注意が必要です。
シニア世代は体力低下、感覚機能の衰え、生活環境の変化により残暑に弱くなります。夏の疲労が蓄積した体には負担がかかり、熱中症リスクが高まります。高齢者は喉の渇きを感じにくく水分摂取が減少しがちです。また、単身世帯では緊急時の対応が遅れる問題もあるため、家族や地域による見守り体制の構築が重要です。
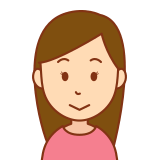
9月に入ってもなお、35度を超える猛暑が続いています。涼しさが訪れず、大変な日々をお過ごしのことと思います。
残暑対策は一人で抱え込まず、家族や周囲の人の協力を得ることが不可欠です。一人暮らしの方には、定期的な電話や訪問、遠隔見守りデバイスを活用して、急変時に早期対応できるようにしましょう。熱中症警戒アラートや暑さ指数(WBGT)をこまめに確認し、警戒日には特に注意してください。
本記事では、残暑に弱いシニア世代の具体的な対策や緊急時の対応、注意事項などについて解説します。
シニア世代が「残暑」に弱い理由
加齢に伴う体の変化が主な要因です。これらの生理的変化により、シニア世代は残暑時期の体調管理に特別な注意が必要となります。
- 喉の渇きを感じにくい:加齢により口渇中枢の機能が鈍化するため、若い世代と比べて水分不足のサインを感じ取りにくくなります。そのため、自覚症状がないまま脱水状態が進行することが多いのです。
- 体内の水分量が少ない:シニア世代は体内の総水分量が若い世代より10~15%程度少ない傾向があります。そのため、わずかな発汗でも体内の水分バランスが崩れやすく、脱水症状に陥りやすくなります。特に残暑期は油断しがちなため注意が必要です。
- 体温調節機能の低下:加齢により発汗機能や皮膚血管の拡張機能が衰えるため、効率的に熱を体外に放出する能力が低下します。その結果、体内に熱がこもりやすくなり、気温上昇に適切に対応できなくなります。この機能低下は残暑期にも継続し、油断すると熱中症のリスクが高まります。
- 持病や服薬の影響:基礎疾患のある方は体温調節機能が低下しています。また、高血圧治療薬、抗ヒスタミン薬、向精神薬などは体温調節を妨げたり、発汗を抑制したり、水分・電解質バランスに影響を与えたりする副作用があります。
これらの理由から、シニア世代は「気づかないうちに体調を崩す」ケースが多く見られます。特に室内や夜間の熱中症にも注意が必要です。

「無理をしないこと」が何よりも大切ですね。服薬中の方は医師に相談し、残暑期の薬の調整や適切な水分補給について指導を受けましょう。
具体的な残暑対策
命を守るためには、自宅、外出時、活動時それぞれの状況に応じた具体的な対策を実践することが重要です。
こまめな水分・塩分補給
喉が渇く前に定時で水分摂取を習慣化しましょう。毎食時、入浴前後、就寝前、起床時にコップ1杯の水分を取ります。水や麦茶だけでなく、経口補水液やスポーツドリンクで電解質も補給しましょう。大量に汗をかいた時は梅干しや塩飴でミネラル補給も効果的です。水分制限がある方や糖尿病の方は医師に相談し、外出時は必ずペットボトルを携帯してください。
室温・湿度管理の徹底
夜間や就寝中の熱中症防止にエアコンを活用しましょう。室温28℃以下、湿度60%以下を目安に、就寝中は27~28℃を維持します。エアコンと扇風機を併用し、すだれやカーテンで日光を遮り、定期的に換気を行いましょう。温度計・湿度計で室内環境を常に確認することが大切です。
服装と身だしなみ
通気性・吸湿性の高い綿や麻素材の、ゆったりした薄手で明るい色の服を選びましょう。外出時は広つばの帽子や日傘で直射日光を避け、屋外でのマスクは必要時以外は外して熱中症リスクを軽減してください。
食事と栄養のバランス
暑さで食欲が落ちても、炭水化物、タンパク質、ビタミン、ミネラルをバランスよく摂取しましょう。味付けを少し濃くしたり、梅干し、塩昆布、味噌汁で適度な塩分を補給します。水分が豊富な果物、ゼリー、冷たいスープ、夏野菜を積極的に活用しましょう。
適切な活動と十分な休息
暑い時間帯(10時~16時)の外出や運動は避け、朝夕の涼しい時間を選びましょう。疲労を感じたらすぐに涼しい場所で休憩をとることが大切です。質の良い睡眠のため、ぬるめの入浴と快適な睡眠環境を整え、昼寝や軽い運動も取り入れて心身をリフレッシュしましょう。
注意すべきサインと緊急時の対応
熱中症は、初期段階での気づきとその対応がとても重要です。
注意すべきサイン
- 初期症状:めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分の悪さ、吐き気、頭痛などです。
- 重症のサイン:意識がもうろうとする、呼びかけに反応しない、体が熱いのに汗が出ない、けいれん、まっすぐに歩けないなどの症状が見られたら、極めて危険な状態です。
緊急時の対応
- すぐに涼しい場所へ移動:エアコンの効いた室内や風通しの良い日陰に避難させます。
- 体を冷やす:衣服をゆるめ、首筋、脇の下、足の付け根などを冷たいタオルや保冷剤で冷やします。
- 水分・塩分を補給:意識がはっきりしている場合は、経口補水液や塩分を含んだ飲み物を少量ずつ飲ませます。
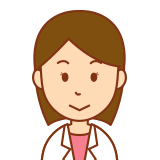
意識がない、呼びかけに反応しない、自力で水分が摂れない場合は、直ちに119番通報してください。
特に気をつけたい注意事項
「まだ暑さは続く」と認識し、日中だけでなく夜間も油断せず、10月まではしっかり対策を継続しましょう。電気代を気にしてエアコンの使用を控えたり、喉の渇きを我慢したりせず、快適さを優先する工夫が大切です。
心臓病や腎臓病で水分制限がある方、利尿剤など薬の影響で脱水になりやすい方は、必ず医師の指示に従い、自己判断での塩分摂取は避けましょう。頭痛、吐き気、倦怠感があればすぐに休養・水分補給し、回復しない場合は速やかに医療機関を受診してください。
定期的に体温・体重・血圧を測定し、体調変化、特に体重の急な減少(脱水のサイン)を見逃さないようにしましょう。残暑は身体だけでなく心にも疲れをもたらすため、無理せず休息を取り、家族や友人との交流で孤立を防ぎ、心身の健康を保つことも重要です。
キーワードは「無理をせず、こまめに、快適に」です。これを意識し、元気に残暑を乗り切りましょう。この三原則を日常に取り入れれば、残暑も健康的に安全に過ごせます。小さな工夫が大きな健康被害の予防につながります。以下に参考として「まとめサイト」をご用意しました。
おわりに
シニア世代の残暑対策は、こまめな水分・塩分摂取、環境調整、適切な服装選び、行動の工夫、そして早期の対応と周囲の人々による積極的な見守りによって、健康維持と命を守ることに直結します。特に体調変化に気づきにくい高齢者にとって、これらの対策は単なる快適さの問題ではなく、生命を守るための重要な取り組みです。
シニア世代にとって残暑は「知らないうちに体調を崩す」危険な時期です。日中も夜間もエアコンや扇風機で室内環境を快適に保ち、喉の渇きを感じる前に水分・栄養補給を行いましょう。外出時は通気性の良い服装で暑い時間帯を避け、体調の変化に敏感になり、違和感があればすぐに休息を取ることが大切です。
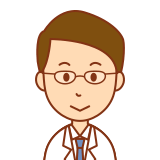
持病がある方や薬の影響で脱水しやすい方は、かかりつけ医に相談し、自分に合った対策を実践しましょう。定期的な健康チェックと医療専門家のアドバイスも欠かせません。
残暑対策は一人で抱え込まず、家族や友人、地域の人々の協力を得ましょう。毎日の声かけや健康チェックを習慣にし、涼しい公共施設も活用して社会的つながりを維持することで、心身の健康を守ることができます。
《 参考情報 》