近年、日本社会において働きながら家族の介護を担う「ビジネスケアラー」が急増しています。2025年には、人口構成で最大規模を占める団塊の世代の全員が後期高齢者となり、介護の必要性がさらに高まるものと予想されます。
この状況は高齢化社会の進展と核家族化を背景としており、多くの働き世代にとって避けられない課題となっています。当事者は仕事と介護の両立に戸惑い、心身に大きな負担を抱えがちです。特に介護の開始時期や期間を予測することが困難なため、長期的な生活設計に支障をきたすことも少なくありません。

私もビジネスケアラーになったのは40代半ばで、その後20年以上も介護を続けることになるとは予想もしていませんでした。当初は親の状態も安定しており、負担も軽度でしたが、時間の経過とともに徐々に重くなっていきました。介護の必要度が増すにつれ、仕事との両立が困難になり、心身の疲労が蓄積していきました。
しかし、適切な心構えと対応方法を身につけ、自身の健康管理を意識することで、この困難を乗り越えることができました。

なかでも重要だったのは、早い段階で周囲のサポートを受け入れる姿勢と、自分自身のケアを怠らないことでした。
本稿では、ビジネスケアラーとしての心構え、具体的な対応方法、そして自身の健康維持のポイントについて、実体験に基づく事例とともに解説します。これから介護に直面する方々や、現在介護中の方々の仕事と介護の両立の一助となれば幸いです。
ビジネスケアラーとしての心構え
まず、介護に直面した際に持つべき心構えについて考えていきましょう。
- 一人で抱え込まないことを第一に 介護には身体的、精神的、経済的な負担が伴います。一人で抱え込むと疲弊してしまうため、「助けを求めることは当然」という意識を持ちましょう。家族や友人、職場の同僚、専門機関など、周りの支援を早めに活用することが大切です。
- 完璧を目指さない 介護に終わりは見えにくく、完璧を目指すと精神的に追い詰められます。「今日はここまでで十分」と、適度な妥協点を見つけることが大切です。介護される方にとっても、介護者の余裕ある状態が望ましいです。
- 長期戦を意識する 介護は数ヶ月から数十年以上続くことがあります。長期的な視点を持ち、無理のないペース配分を心がけましょう。
- 自分の時間も大切に 介護に追われ趣味や楽しみを諦めがちですが、自分の時間を確保する工夫も重要です。それが介護への活力にもなります。
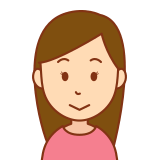
介護される親の状態は日々変化します。その都度、的確な対応方法を模索し、新しい情報や専門家のアドバイスを取り入れる柔軟な姿勢が大切ですね。
具体的な対応方法
介護に直面した際の具体的な対応方法を説明します。最初に必要なのは、介護保険制度や利用可能なサービスについての理解です。
情報収集
- 地域包括支援センター:相談窓口として活用し、ケアマネジャーの紹介や必要な情報提供を受けることができます。
- その他支援:自治体独自の支援制度や民間サービスについても検討しましょう。
協力体制づくり
- 家族との連携:家族間で役割分担を決め、介護方針や費用負担について話し合うことが大切です。
- 職場との調整:早めに上司に相談し、介護休業などの制度を活用しましょう。
- 周囲への相談:友人や知人に相談することで、精神的な負担を軽減できます。
サービス利用
- ケアマネジャー活用:介護計画の作成や各種調整など、積極的に相談することが重要です。
- 介護サービス:デイサービスやショートステイを上手く組み合わせ、介護の負担を減らしましょう。

在宅サービスだけでは介護が困難になった場合は、介護施設の利用を検討することも重要な選択肢ですね。
仕事との両立
- 時間管理:効率的なスケジュール管理を心がけ、介護サポートアプリなどの便利なツールを活用しましょう。
- 離職回避:利用できる制度を最大限に活用し、仕事との両立を目指します。
経済面の準備と緊急時対応
- 費用把握:介護費用の概算を把握し、利用できる支援制度を確認しましょう。
- 連絡網整備:緊急時の連絡先リストを作成し、かかりつけ医との定期的な情報共有も行いましょう。

自分の健康管理の重要性
介護者が心身ともに健康であってこそ、質の高い介護を継続することができます。ご自身の健康管理は、決して後回しにしてはいけません。
身体的健康の維持
- 十分な睡眠の確保:睡眠不足は体力低下だけでなく、集中力や判断力の低下にもつながります。短時間でも質の高い睡眠が取れるよう、寝室環境を整えましょう。必要に応じて、家族や介護サービスを活用して睡眠時間を確保することも大切です。
- バランスの取れた食事:忙しさで食事がおろそかになりがちですが、健康維持には栄養バランスのとれた食事が欠かせません。簡単な食事でも構いませんので、規則正しく食べることを心がけましょう。宅配弁当やミールキットの活用も効果的です。
- 適度な運動:運動は体力維持とストレス解消の両方に効果があります。ウォーキングやストレッチなど、無理のない範囲で日常生活に取り入れましょう。介護の合間にできる簡単な体操も有効です。
- 定期的な健康診断:自身の健康状態を把握するため、定期的に健康診断を受けましょう。早期発見・早期治療が重要です。
精神的健康の維持
- ストレスマネジメント:介護ではストレスが蓄積しやすいものです。趣味の時間、好きな音楽、自然との触れ合い、瞑想など、自分に合ったストレス解消法を見つけ、意識的に実践しましょう。
- 自分の時間を持つ:介護に追われる中でも、意識的に自分の時間を作りましょう。短時間でも、好きなことをする時間は心のリフレッシュになります。
- 専門家のサポート:精神的なつらさを感じたら、一人で抱え込まず、カウンセラーや精神科医などの専門家に相談しましょう。話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になることがあります。
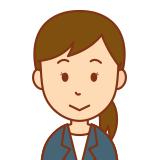
さらに、介護者同士の集まりやオンラインコミュニティに参加し、悩みの共有や情報交換をすることで、大きな精神的支えを得られることもありますね。
おわりに
ビジネスケアラーとして仕事と介護を両立することは、決して簡単ではありません。しかし、適切な情報を得て、制度やサービスを最大限に活用し、周囲の協力を得ながら、そして何よりも自身の心身の健康を大切にすることで、この困難な時期を乗り越えることができます。
介護に没頭すると社会とのつながりが薄れがちです。家族や親類との連絡を意識的に取り、地域活動に参加するなど、社会との接点を保ち続けることが大切です。また、ケアマネージャーや介護ヘルパーなど支えとなる人々との良好な関係を築き、精神的な安定を保ちましょう。
一人で抱え込まず、まずは身近な人や専門機関に相談することから始めてください。あなたをサポートしてくれる人は必ずいます。あなた自身が笑顔でいられることが、介護される方にとっても、またあなた自身の人生にとっても、最も大切なことです。
苦しい介護生活にも、必ず終わりが訪れます。その時は、自分をしっかりと褒めてあげてください。この時期を乗り越えた先には、充実したセカンドライフが待っているはずです。
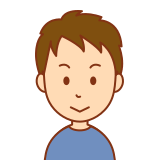
私自身も介護を全うした経験があり、今は自身の健康を大切にしながら充実したセカンドライフを満喫しています。
《 参考情報 》






