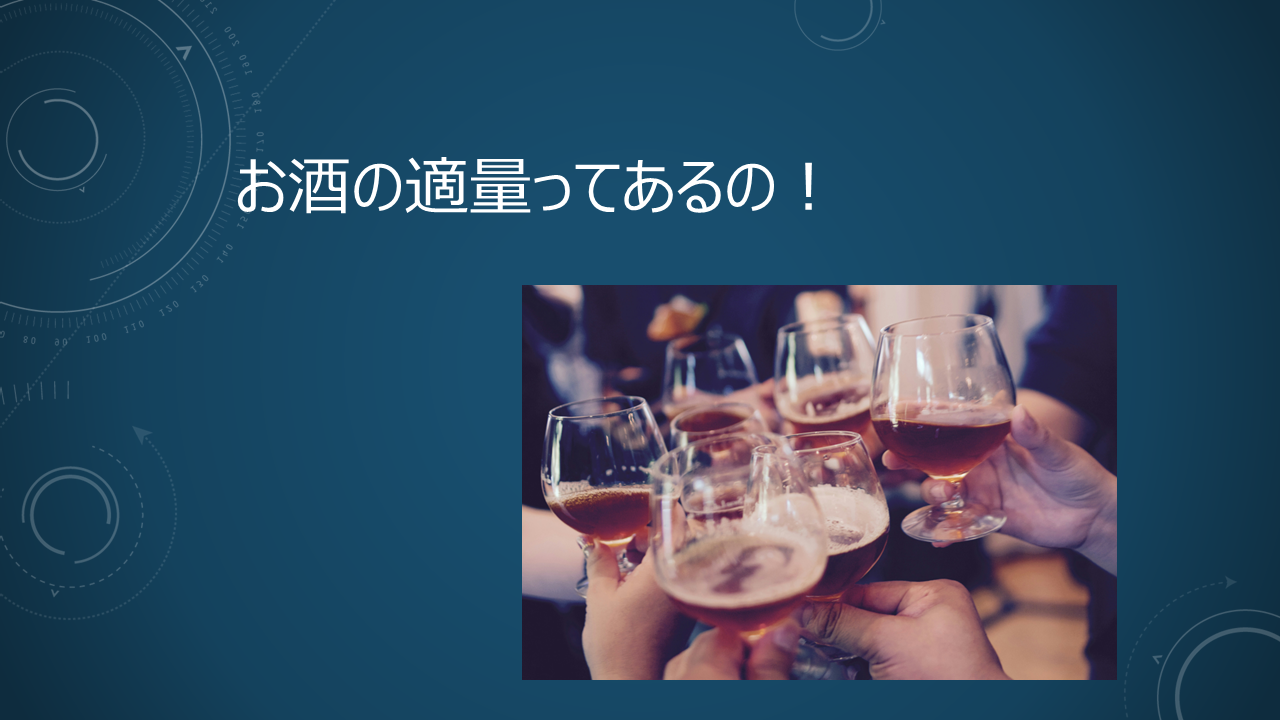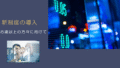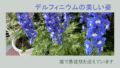お酒を「適量」と言われる範囲で飲んでいても、必ずしも健康が保証されるわけではありません。最新の医学的知見によると、「アルコールには安全な摂取量はなく、少量でも健康リスクがある」という考え方が主流となっています。
遺伝的にアルコールの分解能力が高い方(例えば、アセトアルデヒド脱水素酵素ALDH2の活性が高い場合)でも、「適量」とされる飲酒に健康上のリスクが伴います。また、ストレス解消効果についても、長期的には健康に良いとは言えないことが分かってきています。
以前は心臓病などのリスクを軽減する可能性を示す研究(Jカーブ効果)も存在しましたが、その分析方法には問題点が指摘されています。
世界保健機関(WHO)は「飲酒は健康を損なうだけである」という見解を示しており、日本の厚生労働省が2024年に策定した「飲酒ガイドライン」でも、健康リスクをゼロにする飲酒量は「ゼロ」であると明確に示しています。
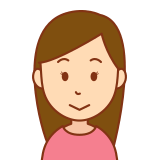
このような状況を踏まえ、酒造メーカーはノンアルコールビールにとどまらず、多様なノンアルコール飲料を展開していますね。
本記事では、アルコールの適正飲酒について、最新の知見に基づいて考察していきます。
最新の飲酒量基準と健康リスク
厚生労働省は2024年に「飲酒ガイドライン」を策定し、アルコール摂取による健康リスクについて科学的知見を総合的に評価しました。以下では、このガイドラインで示された飲酒量基準や健康リスクの主要な点について説明していきます。
飲酒量基準
厚生労働省のガイドラインでは、生活習慣病のリスクを高める飲酒量を、純アルコール摂取量で男性20g/日以上、女性10g/日以上としています。ただし、これはリスクが高まる目安であり、これ以下でも安全とは限りません。純アルコール20gは、ビール中瓶1本(500ml)、日本酒1合(180ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)に相当し、女性はその半分が目安となります。
なお、このガイドラインでは、年齢や性別、体質の3つの要因によりお酒の影響が異なることを指摘しています。具体的には、加齢に伴いアルコールの代謝能力が低下すること、女性は男性より少ない飲酒量で健康リスクが上昇すること、そして遺伝的な体質によってアルコールの分解能力に大きな個人差があることが示されています。
生活習慣病のリスク
- がん: アルコールは口腔・咽頭・喉頭・食道・肝臓・大腸・乳がん(女性)など、多くのがんの確実な原因です。このリスクは少量の飲酒でも上昇します。
- その他の疾患: 高血圧、脳卒中、肝疾患などのリスクは、飲酒量に比例して高まります。
具体的には、1日10gの飲酒で口腔がんが1.8倍、食道がんが4.6倍になるという研究結果が示されています。また、高血圧、脳卒中、肝疾患のリスクも飲酒量に応じて上昇します。長期的な飲酒により、肝臓障害(脂肪肝、肝硬変)や脳機能の低下(認知機能低下、脳萎縮の加速)が起こる可能性もあります。
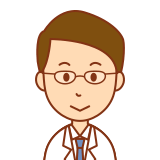
医学的な観点からは、少量の飲酒であっても健康への悪影響が生じる可能性があります。ただし、適量を守る場合、健康リスクは比較的低く、ストレス解消効果を得られることもあります。
アルコール分解能力が高い人のリスク
アルコール分解能力が高い場合、アセトアルデヒドの影響は軽減されますが、その他の健康リスクは依然として存在し、飲酒量の増加に伴いリスクも上昇します。
アセトアルデヒド以外のリスク
アルコールとその代謝物には発がん性や臓器への毒性があります。分解能力が高い人は不快症状や二日酔いを感じにくく、食道がんのリスクも比較的低いものの、肝臓への負担、その他のがん、高血圧、脂質異常症などのリスクは変わらず存在します。
飲酒量増加のリスク
分解能力が高く不快な反応を感じにくい方は、飲酒量が自然と増える傾向があります。その結果、アルコール依存症、肝臓疾患、その他のアルコール関連疾患のリスクが高まります。

もちろん人にもよりますが、お酒に強い人はどうしても飲み過ぎになりやすく、アルコール依存症などになりやすいリスクがありますね。
ストレス解消効果と健康リスク
お酒は従来、職場での円滑なコミュニケーションに不可欠とされてきました。確かにアルコールには、一時的な気分の高揚やリラックス効果があり、仕事のストレス解消に役立つと考えられてきました。しかし近年の研究では、以下のような健康上の問題点が明らかになっています。
一時的な効果と依存性
アルコールによる気分の高揚やリラックス効果は一時的なものです。これは単に脳の機能を一時的に抑制しているだけで、根本的なストレス解決にはなりません。
耐性と離脱症状
継続的な飲酒は「耐性」を引き起こし、同じ効果を得るために必要な量が増えていきます。さらに、アルコールが抜けると不安や不眠などの離脱症状が現れ、新たなストレスを生む悪循環に陥ります。
精神・睡眠への悪影響
長期的な飲酒は睡眠の質、とりわけレム睡眠を低下させ、うつ病や不安障害のリスクを高めてしまいます。ストレス解消には、運動や趣味、友人・家族との対話、十分な休養、そして瞑想やヨガなど、より健康的で継続可能な方法を選びましょう。
依存リスク
ストレス解消のための飲酒は、アルコールへの精神的依存を引き起こしやすく、アルコール使用障害(アルコール依存症)の警告サインとなります。
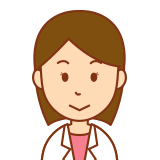
飲酒には社交促進やストレス緩和などの効果があるとされてきましたが、最新の研究では、少量でもリスクが利点を上回ることが示されていますね。
おわりに
遺伝的にアルコール分解能力が高い人でも、「適量」の飲酒であってもアルコールによる健康リスクは避けられない場合があります。また、アルコールによるストレス解消効果は一時的なものであり、長期的には依存症、精神的不調、睡眠障害などのリスクをもたらす可能性があります。
健康を第一に考えるのであれば、飲酒しないことが最も安全な選択です。すでに飲酒習慣がある場合は、健康リスクを認識した上で、摂取量を減らし、定期的な休肝日を設け、体調不良時や服薬中は控えることが重要です。
ストレス対処には、運動(β-エンドルフィン放出)、趣味活動、人との交流、十分な休息、瞑想やヨガ、マインドフルネスなど、より健康的で持続可能な方法があります。ストレスを感じた時は、お酒に安易に頼るのではなく、より健康的な対処方法を見つけることが大切です。
飲酒は「楽しむ程度」に控え、より健康的なストレス管理法を優先することが科学的な観点から推奨されます。その際、お酒のもつ「百薬の長」と「万病のもと」という二面性を十分に理解した上で、適切な量と飲み方を心がけることが重要です。
《 参考情報 》