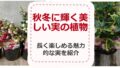OTC類似薬の保険適用見直しは、日本の医療経済の根幹、公的保険制度の将来的な持続可能性、そして一般市民の日常生活や家計に深く関わる極めて重要な政策テーマとなっています。
政府は急速に進む高齢化に伴う医療費の増大という課題に対処するため、この見直しを「経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太の方針2025)」に明確に明記し、2026年度からの段階的かつ計画的な制度変更の実現を目指しています。

この改革の本質は、「ドラッグストアや薬局で手軽に購入できる軽い症状の薬は、公的健康保険を使わず全額自己負担で購入してください」という方向性を示すものです。この変更により、国民の受診行動や薬の入手方法に大きな変化が生じる可能性があります。
本記事では、OTC類似薬の基本的な定義、見直しが検討される社会的・経済的な背景、政府が検討している具体的な見直し案、そして社会全体や国民生活への影響と今後の課題について、できるだけ分かりやすく解説していきます。
OTC類似薬の定義と現状
OTC類似薬とは、「医療用医薬品(医師が処方する薬)」のうち、成分や効能が市販薬(OTC医薬品:Over The Counter医薬品)とほぼ同じものを指します。
どのような薬が含まれるか
OTC類似薬には、日常生活でよく使われる薬が多く含まれています。具体的には、風邪薬、湿布薬(貼り薬。例:ロキソプロフェンパップなど)、鎮痛薬、胃腸薬のほか、乾燥肌の治療に使われる保湿剤(例:ヘパリン類似物質を含むヒルドイドなど)、一部の花粉症薬(例:アレグラ、クラリチンなど)、そしてビタミン剤や一部の漢方薬(例:葛根湯)などです。
現行制度のメリットと焦点
現行制度では、これらの薬は医療機関の処方箋を通じて、公的医療保険の対象となり、患者は原則1〜3割の自己負担で受け取ることができます。これにより、医師の助言を受けながら安価に適切な治療を受けられるメリットがあるとされてきました。

しかし、同じ成分の薬をドラッグストアで購入する場合は全額自己負担(10割)となるため、「病院でもらった方が安い」という価格差が生じており、これが今回の見直しの焦点となっていますね。
政府による見直しの背景と目的
日本は高齢化と医療の高度化により、国民医療費が年間46兆円を超える水準まで増加しています。公的医療保険制度の財政的な持続性確保が喫緊の課題です。
医療費削減と財源確保
見直しの最大の目的は、医療費の削減と保険財源の確保です。OTC類似薬は市販薬で対応できる場合が多く、保険の乱用や受診回数増加による医療費増大が指摘されています。
政府は、セルフメディケーション(自分で健康を管理すること)で対応できる軽度な症状への保険適用を縮小し、浮いた財源を高額な抗がん剤や先進医療など、本当に保険が必要な領域に振り向けたいという狙いがあります。
公平性と適正利用の確保
軽度な不調でも保険で安く薬を受け取る人々と、忙しくて病院に行けず自費で市販薬を買う人々との間に生じる不公平感を解消する目的もあります。さらに、美容目的で保湿剤を大量に処方してもらうといった不適切な利用を防ぐ狙いもあります。
見直しの具体的な内容(検討案)
2025年11月現在、政府・与党が検討している見直し案は、主に以下の3つです。
追加料金を課す案
保険適用は維持しながら、通常の1〜3割負担よりも高い自己負担額を患者に求める案です。無駄な受診や薬の利用を抑制する狙いがあります。選定療養の仕組みを使い、ドラッグストアの価格との差額を上乗せ徴収する方法も検討されています。
保険適用を限定する案
慢性疾患患者や低所得者など、支援が必要な人へのセーフティネットは確保しつつ、それ以外のケースでは自己負担を増やす(または保険適用外とする)案です。
一律で保険対象外とする案
OTC類似薬を公的保険の対象から完全に外し、患者が薬価全額(10割)を自己負担する案です。医療費削減効果は最大(日本総研の試算では約1兆円)と見込まれますが、患者負担も最も大きくなります。
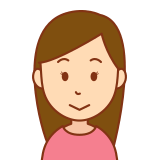
現状の1〜3割負担が一律保険外となれば10割負担となり、年間で数万円から十数万円以上の追加費用が発生する可能性がありますね。
見直しによる影響と課題
医療費・保険財政への影響(メリット)
OTC類似薬の保険適用見直しにより、医療費約1兆円の削減が見込まれます。これは医療保険料率の上昇抑制や現役世代の負担軽減につながる可能性があります。
患者負担と健康格差(デメリット)
患者にとって最大のデメリットは、短期的な家計負担の増加です。特に影響を受けるのは、高齢者や慢性疾患で定期通院し湿布や保湿剤を頻繁に利用する患者、そして低所得層です。負担増により受診控えや健康格差の拡大が懸念されています。

医師会や患者団体の調査では、7割が「保険外し」に反対しており、経済的理由による治療中断への懸念が指摘されています。
医療機関・市場への影響
軽症患者の受診が減れば、病院の待ち時間が緩和され、本当に医師の診察が必要な人がスムーズに受診できるメリットがあります。ただし、受診遅れによる病気の重症化が、結果的に医療コストを増大させる可能性もあります。
保険適用外化により、ドラッグストア業界やOTC医薬品メーカーは売上増が見込まれます。一方で、調剤薬局は処方箋の減少により減収となり、一部のジェネリックメーカーは逆風を受けるリスクがあります。
これらの内容を分かりやすくまとめた動画サイトは、以下のとおりです。ぜひご覧ください。

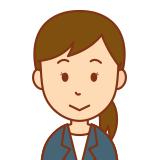
この改革の成否は、低所得者や慢性疾患患者への支援体制を確立できるかどうかにかかっていますね。
おわりに(今後の展望)
OTC類似薬の保険見直しは、公的保険制度の持続可能性を高めるために避けられない改革です。しかし、患者負担の増加、受診行動の変化、健康格差の拡大など、慎重な対応が必要な課題を多数抱えています。
実効性のある改革を実現するためには、以下の要素が不可欠です。
- セーフティネットの確保:子どもや慢性疾患者、低所得者など、影響を受けやすい層への支援(例:高額療養費制度の補完、クーポンや減免制度など)を検討し、実効的な保護を確立すること。
- 段階的実施と評価:短期間で一斉に実施せず、段階的に進めながら影響を評価し、調整を行うこと。
- 薬剤師の役割強化:市販薬の購入が増えることに伴い、薬局・薬剤師による服薬管理、安全管理、薬の過剰摂取や相互作用リスクへの対策を強化すること。
- セルフメディケーションの推進:患者側も、市販薬を年間1万2,000円以上購入した場合に税控除が受けられる「セルフメディケーション税制」を積極的に活用することが賢明です。
政府・与党は、2025年度中に制度の骨子案を作成し、2026年度からの実施を目指しています。「必要な人には支援」「過度な負担につながらない体制整備」「無駄な薬の利用抑制」—このバランスの取れた社会合意の形成が強く求められています。
《 参考情報 》