シニア世代における逆流性食道炎(GERD)は、加齢に伴う身体機能の変化や長年の生活習慣により、発症リスクが高まる消化器系の病気です。胃酸や胃の内容物が食道へ逆流し、食道粘膜に炎症を引き起こします。
胸焼けや呑酸(酸っぱい液体が喉まで上がる感覚)といった症状が慢性的に続くことで、日常生活の快適さや活動性が損なわれ、生活の質(QOL)が大きく低下する可能性があります。
加齢による身体の変化により、シニア世代は逆流性食道炎を発症しやすくなります。胸やけや呑酸(すっぱいものがこみ上げる感じ)、慢性的な咳などの症状が現れ、日常生活の快適さを損なうことがあります。
本記事では、シニア世代に特徴的な逆流性食道炎について解説します。発症の原因やメカニズム、特有の症状、予防法、日常での対策、治療法を分かりやすく説明します。

私自身も胃酸過多の傾向があるため、日頃から逆流性食道炎にならないよう注意しています。
逆流性食道炎が増える主な原因
シニア世代で逆流性食道炎が増える背景には、「防御機能の低下」と「腹圧の上昇」という二つの主要なメカニズムがあります。
防御機能の低下
加齢により、胃と食道の間で逆流を防ぐ下部食道括約筋(LES)の筋力が低下し、弁の役割が弱まります。この筋肉が緩むと、胃酸が食道へ逆流しやすくなります。
また、逆流した胃酸を胃へ押し戻す食道蠕動(ぜんどう)運動も加齢で衰えます。その結果、食道粘膜が酸にさらされる時間が長くなり、炎症が生じやすくなります。さらに、高齢者では唾液の分泌量が減少し、酸を中和する働きが弱まることも、防御機能の低下につながります。
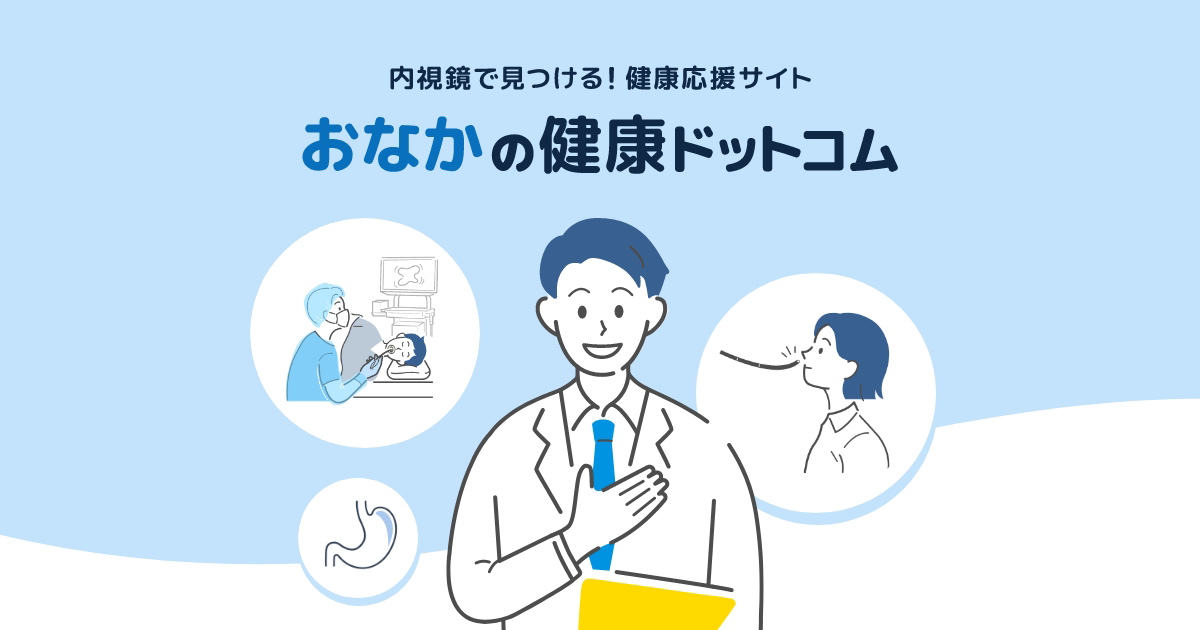
腹圧の上昇
腹部への圧力(腹圧)が高まると、胃が圧迫されて胃内圧が上昇し、逆流が起こりやすくなります。
- 肥満・内臓脂肪の増加:内臓脂肪が増えると腹圧が高まり、リスクが上昇します。
- 姿勢の悪化:猫背や前かがみの姿勢は胃を圧迫する主な原因です。重いものを持つ作業や、長時間前屈みになる生活習慣も影響します。
- その他のリスク:締め付けの強い服装やベルト、便秘時のいきみ、早食いや暴飲暴食、夜遅い食事も腹圧を高めたり、胃酸分泌を促進したりします。
内服薬の影響
高血圧や心臓病の治療薬、喘息治療薬、睡眠薬、抗不安薬など、特定の薬剤がLESを緩める副作用を持つことがあるため、服用中の薬にも注意が必要です。
特有の症状と特徴
逆流性食道炎の代表的な症状は胸焼けや呑酸(酸っぱい物が上がる感じ)ですが、高齢者ではこれらの自覚症状が現れにくいことが特徴です。
- 非典型的な症状:高齢者では、喉の違和感(イガイガ、つかえ感)、慢性的な咳、嚥下障害(飲み込みにくさ)、声がれ、口の苦味、食欲低下など、食道外症状が前面に出ることが多く、喘息や心臓病と間違われることもあります。
- 重症度と症状の不一致:食道の知覚が低下しているため、自覚症状が軽くても、内視鏡検査では食道粘膜の炎症が重症化しているケースがあります。
- 合併症のリスク:炎症が悪化すると、潰瘍や出血、食道狭窄(狭くなること)を起こす恐れがあります。特に夜間の逆流は、胃酸が気管に流れ込む誤嚥性肺炎のリスクを高めます。
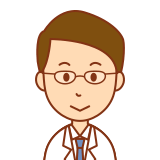
特に、糖尿病や心臓病などの既往疾患を持つシニア世代は、重症化しやすい傾向がありますので、注意が必要です。
予防法と日常生活での対策
逆流性食道炎の予防と症状緩和には、生活習慣の改善が薬物療法と同等、またはそれ以上に重要です。
食事の工夫
- 腹八分目を守る:食べ過ぎや早食いを避けましょう。
- 就寝前の食事を控える:食後2〜3時間は横にならず、夜間の食事は就寝の2時間以上前、理想的には3時間前までに済ませます。
- 刺激物・高脂肪食を制限する:高脂肪食、揚げ物、アルコール、炭酸飲料、コーヒー、柑橘類、甘いもの、刺激物などはLESを緩めたり胃酸分泌を促進したりするため、過剰摂取を控えます。
- よく噛んでゆっくり食べる:一口ずつ丁寧に咀嚼することを心がけます。
姿勢と体重管理
- 腹部を締め付けない服装:きついベルトやコルセット、ガードルは避けましょう。
- 姿勢を正す:猫背や前かがみの姿勢を改善し、重いものを持つ作業や長時間の前屈み姿勢を控えます。
- 適正体重を維持する:肥満傾向がある場合は、ウォーキングなど適度な運動で減量し、腹圧を軽減させることが効果的です。
就寝時の工夫
夜間症状が強い場合は、睡眠時に頭から肩にかけての上半身を10〜20cm程度高くして寝ます(枕を高めにするなど)。
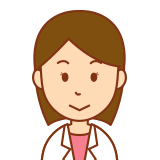
喫煙はLESを緩めるため、禁煙に努め、ストレスを溜めず十分な休息をとることが大切ですね。
治療法
治療は主に薬物療法と生活習慣の見直しで行われます。
薬物療法
胃酸分泌を抑える薬が治療の中心です。
- PPI(プロトンポンプインヒビター):胃酸分泌を強力に抑制し、粘膜の炎症改善や再発防止に効果的です。第一選択薬とされています。
- P-CAB(カリウムイオン競合型アシッドブロッカー):PPIと同様に強力な酸分泌抑制作用を持ち、速効性や安定性に優れています。
- H2ブロッカー:PPIやP-CABより作用は穏やかですが、胃酸分泌を抑制します。
- 必要に応じて、消化管運動機能改善薬や粘膜保護薬が併用されます。
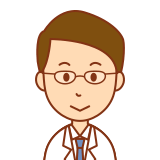
症状が軽くなっても、自己判断で薬を中止せず医師の指示に従うことが重要です。再発や悪化を防ぐためです。
外科手術
薬物療法や生活改善で効果が得られない重症例、食道狭窄や出血がある場合は、抗逆流手術が検討されることがあります。ただし、患者の負担が大きいため慎重な判断が必要です。
これらの内容を分かりやすくまとめた動画サイトは、以下のとおりです。

おわりに
高齢者の逆流性食道炎は、加齢に伴う身体的変化により症状が非典型的になりやすい特徴があります。慢性的な咳、喉の違和感、声のかすれなど、一見すると逆流性食道炎とは無関係に思える症状にも注意が必要です。
早期に正確な診断を受け、生活習慣の改善と適切な薬物療法を並行して行うことが、逆流性食道炎を効果的にコントロールし、QOL(生活の質)を良好に維持する鍵となります。胸やけや喉の違和感、不快感が続く場合は、早めに消化器内科を受診しましょう。
高齢者の多くは複数の疾患を抱え、それに伴い多くの薬を日常的に服用しています。そのため、薬の調整を慎重に行う必要があります。逆流性食道炎の治療薬が他の薬と相互作用を起こしたり、長期服用により副作用(骨粗鬆症のリスク増加や腸内細菌叢への影響など)が現れたりしないよう、医師や薬剤師と連携しながら注意深く管理することが求められます。
高齢者の逆流性食道炎は、年齢による生理的な変化と日常の生活習慣が密接に関係し合っています。日々の予防策を実践しながら、医療機関での適切な診療やケアを上手に活用することで、健康の維持に努めていきましょう。
《 参考情報 》





