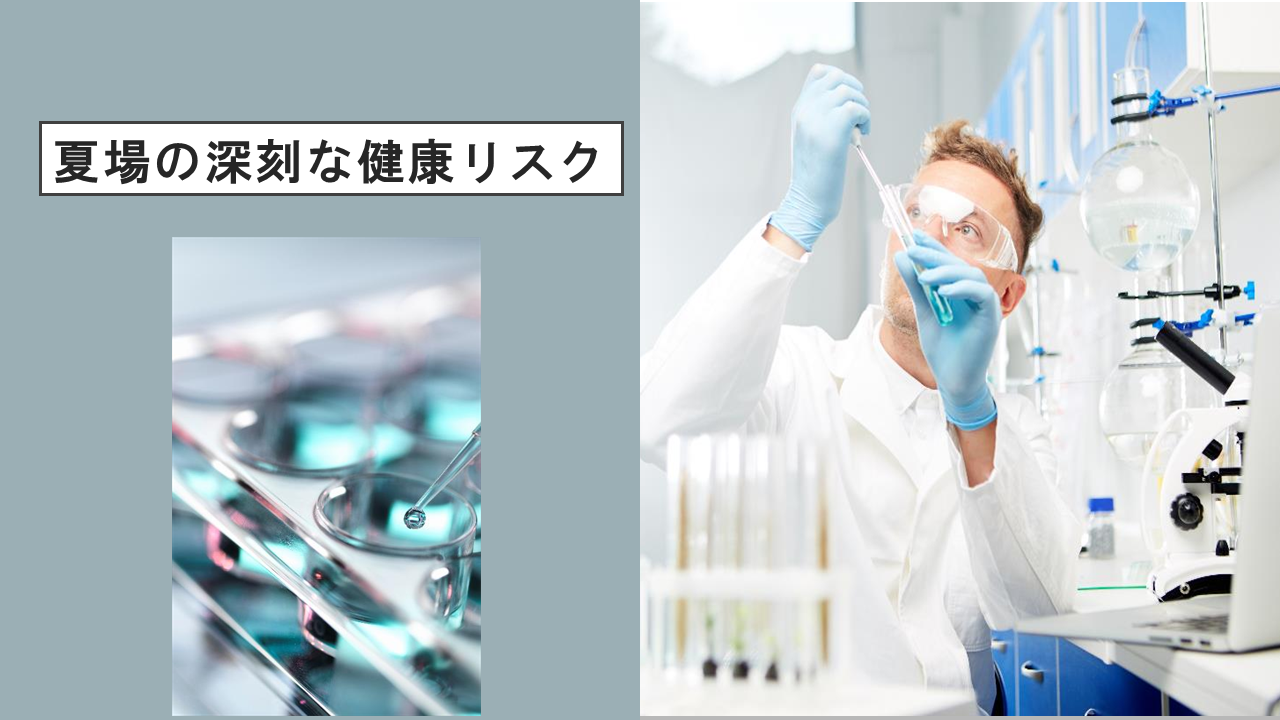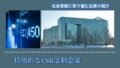シニア世代にとって夏場の細菌性急性胃腸炎は特に深刻な健康リスクです。加齢による免疫力低下や体温調節機能の衰えにより、若年層と比べて明らかに重症化しやすい傾向があります。また、脱水症状が進行しやすく、既存の基礎疾患を悪化させる可能性も高いため、特別な注意が必要です。
特に、細菌性急性胃腸炎は、高齢者が夏場に警戒すべき健康上の脅威の一つです。一般に食中毒として知られるこの疾患は、防御機能が低下しがちな高齢者では症状が急速に悪化するリスクが高く、入院治療が必要になることもあります。
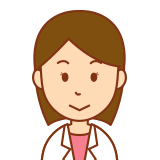
特に水分摂取量が少ない高齢者では、軽度の下痢や嘔吐でも深刻な脱水状態に陥る危険性があります。
本記事では、高齢者が特に注意すべき細菌性急性胃腸炎の主な種類と特徴的な症状、基本原則に基づいた効果的な予防法、そして感染した場合の適切な対処療法について、わかりやすく解説します。

今回は、家族や介護者が知っておくべき早期警告サインや、医療機関を受診すべきタイミングについても説明しますね。
細菌性急性胃腸炎とは?
細菌性急性胃腸炎は、細菌が付着した食品や水を摂取することで発症する消化器系の感染症です。この病態は、腸管内での細菌の異常増殖や、細菌が産生する有害毒素の腸粘膜への作用によって引き起こされます。主な症状には水様性または粘液性の下痢、突発的な嘔吐、腹部の痙攣性疼痛があり、発熱や全身倦怠感を伴うこともあります。
一般的に「食中毒」として知られるこの疾患には、適切な予防と迅速な対応が必要です。特に夏季は気温と湿度の上昇により細菌の増殖が加速するため、食品の取り扱いと保存方法に特別な注意が求められます。

夏に多い細菌性急性胃腸炎の種類と特徴
細菌性腸胃炎にはさまざまな種類がありますが、ここでは夏場に特に感染リスクが高い代表的な細菌をご紹介します。
カンピロバクター
- 原因食品: 生や加熱不十分な鶏肉、鶏レバー、井戸水や沢水など。
- 特徴: 少量の菌でも感染します。潜伏期間が比較的長く(2〜5日、最長で1週間)、発熱、腹痛、下痢、吐き気、頭痛などの症状が現れます。高齢者では特に発熱や腹痛が強く出る傾向があります。回復後、まれにギラン・バレー症候群(手足の麻痺や顔面神経麻痺など)を発症することがあります。
サルモネラ菌
- 原因食品: 生卵や加熱不十分な卵料理、食肉、うなぎなど。
- 特徴: 潜伏期間は8〜48時間程度。38℃以上の高熱、激しい腹痛、水様性の下痢、吐き気、嘔吐などの症状が突然現れることが多いです。高齢者は脱水症状が重症化しやすく、敗血症などの合併症を引き起こすリスクもあります。
腸管出血性大腸菌(O157など)
- 原因食品: 生肉や加熱不十分な肉、野菜、飲料水など。
- 特徴: 潜伏期間は4〜8日。強い腹痛を伴う下痢から始まり、次第に血の混じった便(血便)が出るようになるのが特徴です。高齢者は、溶血性尿毒症症候群(HUS)という重篤な合併症を引き起こすリスクがあります。これは、腎臓や脳に障害を引き起こし、命に関わることもあります。
黄色ブドウ球菌
- 原因食品: おにぎり、サンドイッチ、弁当、餅、ケーキなど。
- 特徴: この菌は食品中で毒素(エンテロトキシン)を生成し、これを摂取することで発症します。菌自体を殺菌しても毒素は残るため、食品の管理が重要です。潜伏期間が1〜5時間と非常に短いのが特徴で、激しい吐き気、嘔吐、腹痛が突然起こります。熱はあまり出ません。
高齢者が特に注意すべき理由
シニア世代が加齢に伴い細菌性腸胃炎に罹患すると、以下の理由から特に注意が必要です。
- 免疫力の低下: 免疫機能が衰えているため、細菌に対する抵抗力が弱く、感染しやすく、症状も重症化しやすいです。
- 脱水症状の重症化: 下痢や嘔吐によって体内の水分と電解質が急速に失われます。高齢者は喉の渇きを感じにくいため、脱水が進行していることに気づきにくく、症状が重症化しやすいです。
- 持病の悪化: 心臓病、腎臓病、糖尿病などの持病がある場合、脱水や発熱によって基礎疾患が悪化するリスクが高まります。
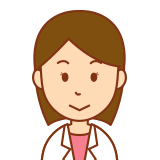
カンピロバクター感染後のギラン・バレー症候群や、O157感染による溶血性尿毒症症候群など、命に関わる重篤な合併症を引き起こす危険性がありますね。
細菌性急性胃腸炎の予防法
予防の基本は「つけない、増やさない、やっつける」の3原則です。
つけない(清潔)
- こまめな手洗い: 調理前、食事前、トイレの後は、石鹸を使って丁寧に手を洗いましょう。
- 調理器具の洗浄・消毒: 生肉や魚を切った後のまな板や包丁は、熱湯消毒や塩素系漂白剤でしっかりと殺菌しましょう。
- 食材の分別: 肉や魚、野菜など、食材ごとにまな板や包丁を使い分けるか、使用前に洗剤でよく洗いましょう。
増やさない(迅速・低温)
- 常温での放置を避ける: 食品はすぐに冷蔵庫に入れ、細菌が増殖しやすい温度帯(10℃〜60℃)での放置は避けましょう。
- 冷蔵庫の詰めすぎに注意: 冷蔵庫に食品を詰め込みすぎると、冷気の循環が悪くなり、十分な冷却効果が得られません。
やっつける(加熱)
- 中心部までしっかり加熱: 細菌は熱に弱いため、肉や魚は中心部の色が変わるまでしっかりと加熱しましょう。特に鶏肉は念入りに加熱することが重要です。
- 二枚貝の加熱: アサリやシジミなどの二枚貝は、加熱しても死なない菌がいる場合があるため、生食は避けましょう。
細菌性急性胃腸炎の治療法と対策
細菌性急性胃腸炎の治療は、症状を和らげる対症療法が中心です。
- 水分補給の徹底:下痢や嘔吐がひどい場合、脱水防止が最優先です。経口補水液を少量ずつこまめに摂取しましょう。スポーツドリンクも代用できますが、糖分が多いため飲みすぎに注意が必要です。
- 安静と食事の工夫:
- 十分な休養を取り、体力回復に努めましょう。
- 吐き気がある間は無理に食事せず、症状が落ち着いてから消化の良いもの(おかゆ、うどん、すりおろしりんごなど)を少しずつ食べましょう。
- 症状が治まるまでは、油っこいもの、香辛料、乳製品、冷たいものは避けるのが無難です。
- 自己判断で下痢止めは使わない:下痢は体が細菌や毒素を排出しようとする防御反応です。自己判断で下痢止め薬を使うと、有害物質が体内に留まり、症状が悪化する恐れがあります。
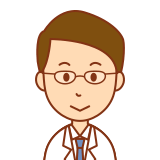
下痢や嘔吐が止まらない、水分が摂れない、高熱が続く、血便が出た、ぐったりしている、意識がはっきりしないなどの症状がある場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。特に高齢者は脱水が急速に進行することがあるため、迷わず医師の診察を受けてください。
おわりに
夏場は細菌性急性胃腸炎の発症リスクが高まります。特に高齢者は免疫力低下により症状が現れやすく、また重症化しやすいため、予防策の徹底と迅速な対応が不可欠です。家庭内や高齢者施設でも継続的な衛生管理と健康観察を心がけましょう。
紹介した予防策を実践することでリスクを低減できますが、感染リスクを完全になくすことは困難です。下痢、嘔吐、腹痛などの疑わしい症状が現れたら、自己判断を避け、早期に医療機関を受診しましょう。早期治療が重症化防止と回復促進の鍵となります。
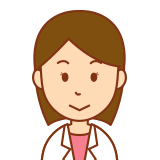
血便、38度以上の高熱、意識障害、極度の脱力感、尿量減少などの全身状態の変化は重篤な状態を示している可能性があります。このような症状が見られる場合は、迷わず救急医療サービスを要請してください。
細菌性急性胃腸炎は正しい知識と適切な予防策で多くを防ぐことができます。夏場は特に手洗い、食品の温度管理、調理器具の清潔な取り扱いなどの基本的な衛生管理を徹底し、体調不良を感じたら速やかに対応することが健康を守る基盤となります。
《 参考情報 》