日本の防衛産業は、長年にわたる武器輸出三原則の厳格な制約により、主に国内市場(自衛隊)に大きく依存する構造が固定化され、国際市場での競争力が著しく低下するという深刻な課題を抱えてきました。
この市場の閉鎖性により、生産規模が限定的となり、スケールメリットを活かしたコスト削減が進まず、結果として国産装備品は海外製品と比較して割高になる傾向が顕著でした。このコスト高は防衛予算の効率的な活用を妨げる要因ともなっています。
また、防衛産業には構造的問題も存在します。大手メーカーでは防衛事業の売上比率が低く経営優先度が高くない一方、特定の中小企業では防衛需要への依存度が極めて高いという不均衡があります。この構造的アンバランスが技術革新と産業の持続的発展を妨げています。
国際情勢の緊張化と日本の防衛費増額方針、東アジア地域の地政学的変化により、国内防衛関連企業は大きな転換点を迎えています。これは新たな事業機会拡大の可能性を高め、防衛装備移転三原則への政策転換も追い風となり、国内外での需要拡大が期待されています。

近年、米国政府は自由主義社会を守るという名目のもと、同盟国や友好国に対して防衛費の大幅な増強を積極的に求める外交姿勢を強めていますね。
このような環境変化の中で、本記事では特に将来性が有望と思われる企業を選定し、その主な課題と事業の有望性や内容について以下で考察します。
主な課題
各社は異なる領域で日本の防衛力強化に貢献し、成長が期待されます。しかし、産業全体には重要課題が存在し、その解決が競争力強化と持続的発展に不可欠です。
- 市場の限定性: 武器輸出三原則緩和後も実質的な輸出は限られ、国内市場への依存が続いています。この構造では規模の経済が活かせず、国際競争力の獲得が困難です。

- コスト構造: 少量多品種生産が中心のため大量生産によるコスト削減が難しく、装備品の調達単価や維持費が増加傾向にあります。
- サプライチェーンの脆弱性: 製造設備の脆弱化や事業撤退により防衛生産・技術基盤が弱体化し、部品供給網の維持が困難になりつつあります。
- 研究開発体制: 「防衛ムラ」中心の旧式体制では民生技術の活用が不十分で、閉鎖的な開発モデルにより技術格差拡大のリスクがあります。
- 人材不足: 少子高齢化による労働力減少が人材確保に影響し、専門知識・技術分野での人材育成と確保、技術伝承が課題となっています。
主な有力企業
日本の防衛産業には様々な企業が貢献していますが、特に貢献度の高い有力企業として以下が挙げられます。
三菱重工業
- 有望な理由: 日本最大の防衛産業企業として、陸・海・空・宇宙全域の基幹防衛装備品を開発しています。戦闘機、潜水艦、護衛艦、戦車、ミサイルなど多様な製品を手がけ、防衛力の中核を担っています。今後は新規装備開発や既存装備のアップグレードで主導的役割が期待されています。
- 具体的な内容: 次期戦闘機開発の主要企業であり、近年では防衛省が重視するスタンド・オフ・ミサイル(長射程ミサイル)の開発にも積極的に取り組んでいます。海上自衛隊の最新鋭護衛艦の建造も担うなど、その事業領域は広範に及びます。
- 今後の展望: 防衛費増額や装備品の高性能化により、引き続き中核的な役割を担うでしょう。陸・海・空の全領域での技術力と納入実績が、今後の受注拡大に直結します。
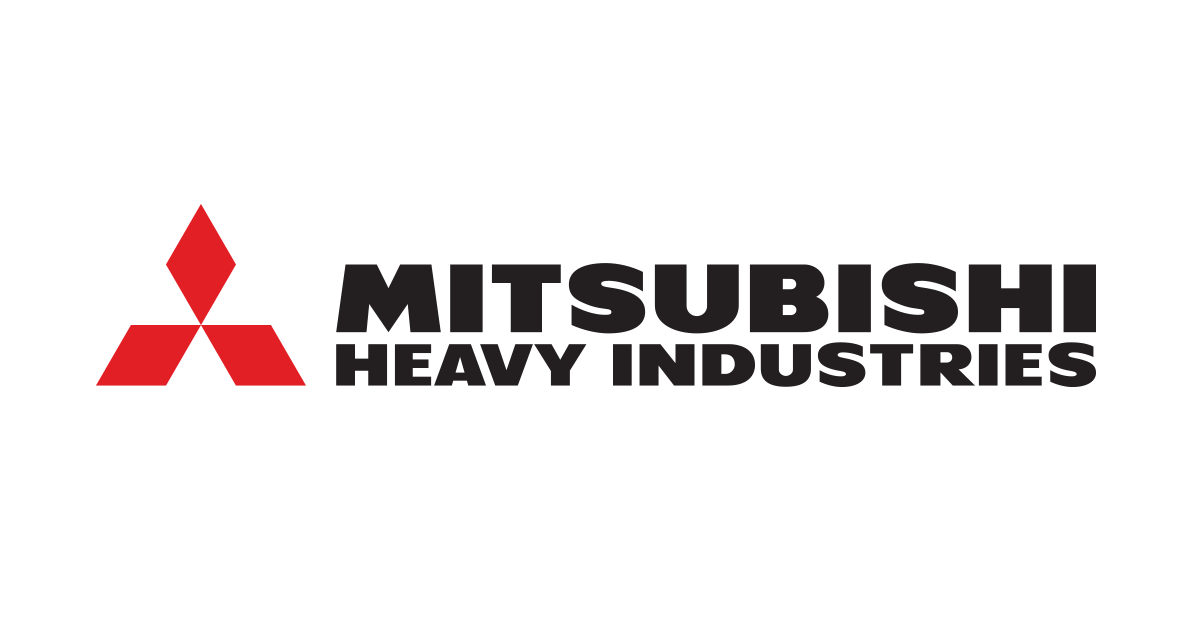
IHI
- 有望な理由: 国内唯一の航空機ジェットエンジンメーカーとして日本の航空防衛力に重要な役割を担っています。次期戦闘機開発において、エンジンの国産化・高性能化は防衛戦略上不可欠であり、IHIが中心的役割を果たすことが確実視されています。
- 具体的な内容: 航空自衛隊の各種航空機用エンジンの開発・製造・メンテナンスを行っています。F-35戦闘機のエンジン部品製造や将来戦闘機用エンジン開発は、日本の航空防衛技術の自立性向上に不可欠であり、IHIの長期成長基盤となります。
- 今後の展望: 次期戦闘機や宇宙防衛インフラの拡充に伴い、受注・売上の拡大が期待されています。多領域連携や国際共同開発の中核企業としても注目を集めています。
日本製鋼所(JSW)
- 有望な理由: 国内唯一の大型火砲メーカーであり、装甲車やミサイル発射筒なども手がけています。火砲・装甲車・レールガンなど陸上装備で独自性を発揮しています。2025年3月期の防衛事業受注額は過去最高を記録し、今後も大幅な成長が見込まれています。
- 具体的な内容: 火砲システムのリーディングカンパニーとしての地位を維持しています。創業以来培ってきた素材・機械製造技術を基盤に、先端技術を開発・適用し、防衛機器の設計・製造・整備や研究開発に取り組んでいます。
- 今後の展望: 防衛省の装備近代化や新型艦艇への装備需要増加により、安定した成長が期待できます。中期的な生産体制強化と新技術開発で、さらなるシェア拡大を目指しています。

これらの企業は、それぞれの専門分野で日本の防衛力強化に不可欠な技術と製品を提供しています。防衛費増額と防衛戦略の変化に伴い、今後さらにその存在感を高めていくと予想されます。
業界展望
- 政策後押し: 防衛装備移転三原則の緩和により、日本企業の防衛装備品輸出拡大の可能性が開かれています。特に東南アジア向け艦艇・レーダーシステム輸出が推進される見込みで、国内市場依存からの脱却と新たな成長機会が生まれています。
- 株価動向: 防衛関連企業の株価は上昇トレンドにあり、三菱重工業は2022年以降10倍超の上昇、IHIも35年ぶりの高値更新など、市場評価が高まっています。この傾向は国際情勢の変化と防衛政策の転換を反映しています。
- リスク: 国際市場でのコスト競争力の弱さ(国産品は輸入品より高価)や防衛費増額の恒久財源未確定など、長期成長を阻害する要因も存在します。これらの課題の克服が持続的発展には不可欠です。
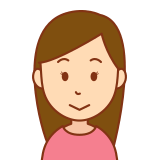
三菱重工業の株価は2022年以降急激に上昇しています。また、IHIの株価も好調であり、今後も防衛産業関連の株価動向に注目していきたいと思いますね。
最後に
現在、日本の防衛費はGDP比で約1.6%(2025年度見通し)であり、政府は2027年度までに2%とする目標を掲げ、毎年約1兆円ペースで増額しています。日本政府は安全保障環境の悪化に対応するため、防衛産業強化を急務とし、様々な政策を展開しています。また、米国も日本の防衛費の増強を求めています。
アメリカからはGDP比3.5%への大幅増額要求が出ており、これは現状の約2倍、20兆円規模に達します。日本政府は「日本が決めるべきもの」と反発していますが、今後の防衛費は、この米国の要求と日本の財政状況、防衛力強化の必要性のバランスを考慮しながら、さらに増加していくものと予想されます。特に、スタンド・オフ防衛能力や統合防空ミサイル防衛能力などの整備が加速するでしょう。
世界情勢の不安定化により、戦争や紛争が絶えない現状においては、防衛費の増強は不可欠なものになりつつあります。また、防衛費の増強は近隣諸国からの圧力に屈しない原動力にもなります。
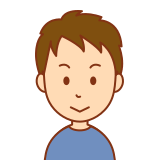
シニア世代の皆様も、今一度それぞれの立場から日本の防衛力の在り方を考察してみてはいかがでしょうか。
《 参考情報 》





